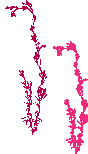終了レポート
「その“サーモン”どこから来たの?2019 ~海と日本PROJECT~」
- 日 程 :
- 9月8日(日)13:00~15:00
- 開催場所:
- 千歳市 サケのふるさと千歳水族館 2階学習室
- 参加者数:
- 31名
- 主 催 :
- サケのふるさと千歳水族館
- 共 催 :
- 北海道大学大学院水産科学研究院
株式会社ダブリュ・コーポレーション/北々亭 千歳店
- 目 的 :
- サケのふるさと千歳水族館は、北の「海の宝」の代表格である「サケ」を中心とした飼育・展示と「サケ」を通した教育活動を25年間に渡り実施してきています。本イベントでは、同水族館と北海道大学大学院水産科学研究院および回転寿司店を北海道内で展開している企業とが協力し、寿司ネタとしての「サーモン・サケ」に焦点を当て、座学、解剖、調理、試食といった五感で体験する食育により、「海の宝:サーモン・サケ」を理解してもらうこと、および本事業の一環で開催する中高生向けの「海の宝アカデミックコンテスト」の周知をすることで、次世代を担う若者に「海や水産」への興味や関心を高めてもらうことを目的としました。
イベント内容
9月8日(日)の午後に、今年9月で開館25周年を迎える「サケのふるさと千歳水族館」において、事前に参加申込をされた31名(うち、高校生3名、中学生2名、小学生11名)の参加者に対し、寿司ネタとしての「サーモン・サケ」をテーマとして、プレゼンテーションによる学びと実際に食材に触れて、自ら寿司を握って食する体験学習を行いました。
イベントは以下のように実施されました。同水族館では、9月に入りインディアン水車でのサケの捕獲がはじまり、水中観察窓でもサケの遡上が見られ、さらには、真っ赤になったベニザケ親魚の展示も始まった本格的なサケ遡上シーズンの開館中に行われました。食材の準備や衛生面の都合、参加者は事前申込者に限定しました。菊池基弘館長の司会進行によりスタートし、前半には、北海道大学大学院水産科学研究院からサケ関連の教員(工藤秀明:本事業実行委員)により、「美味しいお寿司を食べる前に ちょっとサケのお勉強!」というタイトルで、サケの仲間の種類、一般に「サーモン」と言われている魚は何なのか?、世界各地の養殖サーモン、北海道には天然のサケが存在するなどをスライドや動画を交えて説明がありました。プレゼンの最後には、11月に開催する「海の宝アカデミックコンテスト2019 全国大会 -海と日本PROJECT-」に関して、スライドとチラシを使いながら概要、応募方法などが説明されました。休憩を挟んだ後半では、回転寿司店の「北々亭」から提供された、サーモン寿司ネタの食材を見せていただきました。体重 5 kgもある尾頭付きのノルウェー産タイセイヨウサケ(アトランテックサーモン)、チリ産トラウトサーモン(海面養殖ニジマス:フィレ)、日高産シロザケ(ブランドサケ「銀聖」:フィレ)、支笏湖産ヒメマス(湖沼型ベニザケ)を目の前にして、前半に習ったサケの仲間の特徴を実際に確認したりもしました。次に、ダブリュ・コーポレーションの高尾祐也氏によるタイセイヨウサケの解体ショーとして、華麗な「三枚卸し」を見せていただき、部位による味や食感の違いなどの説明もしていただきました。続いて、参加者の皆さんは手洗い・消毒の後、実際に北々亭の店長さんはじめ職人さん達から直接教えていただきながら、シャリ玉の扱いから、4種類のサーモン・サケのネタを使って自分で寿司を握る体験を行いました。すぐに上手に握れる子もいて職人さん達も驚いていたようでした。このイベントでは、寿司ロボット(自動シャリ玉&海苔巻き作製機)の展示も行われ、自分で巻いた手巻きとロボット作のものの比較もできました。各自、お好みの大きさ・形の『サーモンオレンジ』に輝く寿司をお皿に載せて完成です。試食タイムでは、自分で握った4種のサーモン・サケを食べ比べ、「おいしい〜」との声と笑顔のなか、海の畑からの養殖サーモンと海や湖で放牧されていた天然サケのそれぞれの「海の宝」の特徴を理解して、味わっていかれたようでした。最後には、参加者全員で記念撮影を行いました。
イベント開催にあたっては、ダブリュ・コーポレーション/北々亭の皆様および寿司ロボットの展示をしていただいた北海道鈴茂販売の後藤 肇氏には多大なるご協力を得たことを付記します。

菊池館長による司会進行と配布された缶バッチ

サケ研究者によるサーモン・サケのレクチャー

実習の食材とサーモンの解体ショー

真剣な面持ちでお寿司を握る参加者

参加者が握った4種のサーモン&サケ

参加者の皆さんで記念撮影
(工藤 秀明)